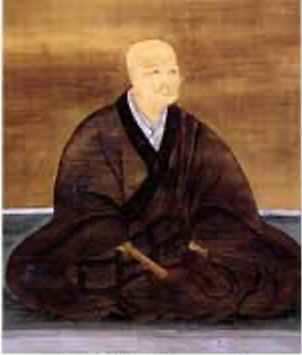香を学ぶ

香りの世界を共に学びましょう。
香木
香木といっても、木そのものが芳香を放つのではありません。
自然に枯死したり、バクテリアによって朽ちた木の樹脂が土中に埋もれている間に木質に沈着し、それを熱するとそれぞれ特有な強いかおりを発します。その特有な香気を聞きわけるのが、香道の第一歩です。
木所
「六国の伝」などというところからも察せられるように、その名はそれを産出した国の名や地方の名であったらしいのです。
マラッカやスマトラなど、その原産地は東南アジアやインドです。残念ながら日本にも中国にも産出しません。
六国五味りっこくごみ
香の世界で現在もちいられている香は、以下の六国五味の「六国」の六種類と「五味」の五種類に分類されます。
六国
「伽羅、羅国、真南蛮、真那賀、佐曽羅、寸門多羅」の六つに分類するものです。
昔は初めの四種だけでしたが、二種が加えられて六種になり、これを六国列香などといいます。その後に新伽羅の一種が加えられたりしましたが、今は敢えて新伽羅に分類することはありません。
五味
香の銘
そこで、それらのいちいちに、固有の名前がつけられています。それが香の銘なのです。
銘香の由来
香銘をつけるにも、出所銘,天体銘,色体銘,貴人銘,故実銘,草花銘,動物銘,文学銘などがあります。
-

出所銘
「東大寺」「法隆寺」「園城寺」など
香木の出所による銘 -

色体銘
「縮黒」「紅塵」「白雲」など
香木の形や色、つやや状況による銘 -

詩歌銘
「柴舟」「春風」「乙女」など
詩歌にちなんだ銘 -

草花銘
「夕顔」「秋蘭」「すみれ」など
草花にちなんだ銘 -

故実銘
「太子」「蘭奢待」「吐月」など
故実による銘 -

貴人銘
「楊貴妃」「中川」「清水」など
姓字からつけられた銘
銘香の歴史
-

蘭奢待らんじゃたい
有名な蘭奢待は、正倉院の御物で、1.54メートルもある大きな伽羅香木です。
これから香を切り取ったのは、足利義政と織田信長とそして明治天皇が著名です。
織田信長がこれを切り取ったということは歴史上に有名ですが、実際に切ったのは一寸(3センチ)角二個というわずかな量でした。さらに信長はその一個を後土御門天皇に献上し、もう一個を三分して、三分の一だけを自分のものにし、あとの三分の二を大名小名に分けて下賜したといいます。
このように、名香の香木はこんなにも大事にされているのです。 -

柴舟
柴舟という銘香には、別の人が「初音」「白菊」「藤袴」という銘も付けていて、一木四銘の銘香といわれています。
同一の香木を京都の御所と前田家、細川家、伊達家で分けあったとき、それぞれに銘をつけたからだといいつたえられています。 -

勅銘香
「春山風」「白雲」「蝉の羽衣」などは、勅銘香といわれます。
後陽成天皇や後水尾天皇がつけた銘で、家元宗匠らによって大事に秘蔵されています。
香道の流派
香道の道具や作法が今日に見られるようなものにまでととのうのは、江戸時代のことですがその源をさかのぼると、日本の香道の流派や家元は、みなこの二流からわかれたものなのです。
-

香道御家流 初代 三條西実隆

鎌倉時代に宮中や京都の公卿の生活状況がにわかに変化して、平安朝のみやびやかな文化がおとろえ、香を味わい楽しむなどということもすたれてきました。
ことに建武の中興からのち、うちつづく戦塵のうちに、そのゆとりはいよいよ失われていきました。それでも宮中でだけは、折々に香を聞く催しが行われていました。
公卿の多くが戦火を避けて地方に都落ちしてしまったあと、残された少数の公卿たちにより、天皇を中心に、歌とか詩とか香といったものが奉仕されていました。香道の御家流の始祖だといわれる三條西実隆も、こうした公卿のうちの一人でした。宮中の御香所預りという役に任命されていました。
これら貴族社会で伝統的に楽しまれていたのは、六種の薫物(むくさのたきもの)という形にまとめられています。その調合法はそれぞれの家に秘法として伝えられたものでした。 -

志野流 初代 志野宗信

室町時代後期、第八代征夷大将軍足利義政は東山殿に文化人を集めた文化サロンを開き、香を聞く会がさかんに催されるようになりました。
この頃より中国から安定的に供給されていた香木を、調合せず天然の贈物である香木を純粋に鑑賞するのです。応仁の乱で、人心が極度にまで悪化し、心あるものは世をのがれて山野にかくれてしまいました。将軍義政の近習だった志野宗信もまたその一人で、職を捨て、宗砥法師や牡丹花肖柏や相阿弥や村田珠光らを風流の友として、茶を喫したり香を聞いたりして、ひそかに風雅の道を楽しんでいました。そしてのちにまた義政に仕えることになったとき、将軍義政にも茶や香や連歌をすすめ、険悪な世相のなかに一脈の温雅な思想を注入しようとしました。義政もこれを喜んで、宗信に香を、珠光に茶を、それぞれ専門に研究させました。
そこで宗信は、古来の香式を学び、旧来の方式を改めて、新しい香道の方式を定めました。これとならんで、珠光は茶道の方式を確立しました。そして香道と茶道がならんで流行することになったのです。